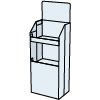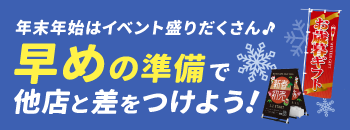目立つのぼり旗の基準とは?

のぼりを目立たせ、集客につなげるためには、「アピールする商品や内容とデザインのギャップがないこと」と「視認しやすく目を引く配色を使っているデザイン」が大切です。また目を引くデザインをつくるうえでは「一目で見てわかること」や「景観との兼ね合い」「色の組み合わせ」など、さまざまな観点から総合的に判断して制作する必要があります。
ただし、自分で一から制作しなくても、既製品ののぼりで十分対応できる場合もあります。本記事では、目立つのぼりはどのようなものか制作する際や選ぶうえでのポイントを詳しく説明していきます。
目立つのぼり旗を使う上で抑えるべきポイント
目立つのぼり旗を使う上で抑えるべきことは、「視認しやすく目を引く配色を使っているデザイン」と「アピールする商品や内容とデザインのギャップがないこと」の2つです。
また、上記のポイントを抑えた目立つデザインののぼり旗を利用するには、既製品を購入する方法と、自分でデザインして発注する方法の2つがあり、いずれの方法でもネット上ののぼり旗製造・直売専門店で注文可能です。
「のぼりキング」の場合は、約6,000点の中から既製品を選んで購入することはもちろん、既製品のテキストや配色、サイズ・生地変更のほか、名入れ印刷ができる「セミオーダー」も可能です。一からデザインしなくても、扱う商材に合ったデザインを見つけられる可能性があります。
どんなデザインが良いか見当をつけたら、既製品を検索し、見合うものがなければ自作でデザインする流れがスムーズです。
景観の中で目を惹くのぼり旗にする
視認しやすく目を引く配色を使っているデザインののぼり旗であるために重要な視点の1つ目は、「周囲の景観との兼ね合い」です。たとえば、のぼりを設置する建物や道路で使っていない色ののぼり旗にすることで、はっきりと目立つのぼり旗になります。比較的交通量の多い都会などでは明るい色が多いので、闇雲に派手な色を使っても、かえって目立ちにくくなってしまうこともあります。
周囲の景観との兼ね合いを考える際には、色相や彩度、明度という指標を知っておくと便利です。これらは「色の三属性」と呼ばれるもので、色相は色の相違、彩度は色の鮮やかさの度合い、明度は色の明るさの度合いを指します。
のぼりをデザインするときは、のぼりと、のぼりを置く場所の景観の色の三属性を対照的にすると、のぼりを目立たせることができます。

たとえば、周囲が緑であれば補色にあたる紫を用い、落ち着いた色味であれば派手に、暗ければ明るい色をといった色を使うと良いでしょう。
また、目立つことをより追求したければ、「錯視」や「誘目性」の考え方に着目するとさらに人の目を引くデザインにすることができます。静止画が動いて見えるようなものを錯視アートなどと呼びますが、色にも錯視があります。色の組み合わせによっては、同じのぼりデザインでも周囲の環境によって見え方が異なることがあり、ある特定の色だけが目立ったり、浮き上がって見えたりすることがあります。


誘目性の違い:▲寒色系(左)と暖色系(右)
「誘目性」は視界に入ったときに目に飛び込んできやすい色を差し、青や緑などの寒色系よりも赤や橙の暖色系のほうが目立ちやすいことが、航空医実験体報告の調査により明らかになっています。周囲の景観とも兼ね合いなど、配慮すべき点は他にもありますが、誘目性の観点に立てば、暖色系の色を用いたほうが目立つのぼり旗をつくることができます。
景観の中でのぼりが目立つかどうか確認するには、実際の設置場所の写真を撮り、その中にのぼりのデザインを重ねて印象を見る方法があります。集客したい時間帯や天気ごとの写真を数枚用意して比較し、どのデザインが目立つか比較すると良いでしょう。
一目で内容の分かるデザインののぼり旗にする
のぼりを目立たせるために重要な視点であるアピールする商品や内容とデザインのギャップがないのぼり旗の基準は「一目で内容の分かるデザインののぼり旗にすること」です。のぼりを目立たせて集客に繋げるためには、走っている車や遠くからでも、のぼりの存在に気づくだけでなく、お店の雰囲気やサービス内容を伝えることが必要になります。
一目で内容がわかるデザインのテクニックの一つとして「文字の縁取り」があります。ただし、色の配色や景観によってはかえって目立たなくなってしまう場合もあるので、前述のように縁取りあり・なしの、のぼりデザインを設置場所の写真のうえに置いて見比べてみると良いでしょう。
お店の雰囲気やサービス内容に合った配色・デザイン


目立つ配色のデザインをしたとしても、お店の雰囲気やサービス内容に合っていないと来客や購買に繋がらないことがあります。
例えば、上記は同じアイスコーヒーののぼりでも、左はシックで上質なデザインなため、落ち着いた雰囲気の喫茶店などに向いており、右はかわいらしくて親しみやすいデザインなため、若者向けのポップなお店に向いています。
具体的には、下記のような方法で、お店の雰囲気やサービス内容を表現することができます。
- ・色彩心理学を参考に、来店する人に感じてほしいイメージを持っている色を選ぶ
- ・お店のイメージカラーを使う
- ・季節のメニューを表す場合は、店で売るものの価格帯(高級感)を基準にする
- ・店でどんな時間を過ごしてほしいかを書き出してデザインに落としこむ
上記の中で、イメージがつきにくいのは色彩心理学でしょう。色彩心理学は、色のイメージを表現する際に便利な学問です。たとえば、赤ならば情熱的、緑ならばやすらぎ、黒は孤独や威厳といったイメージなどが挙げられます。およそ想像はつくかと思いますが、気になる方はインターネットでも十分な知識が得られるので、検索してみると良いでしょう。
雰囲気に合った文字フォントを選ぶ
雰囲気に合ったデザインという観点で言えば、文字フォントも重要です。たとえば、明朝体であれば「大人っぽい」「真面目」、ゴシック体であれば「子供っぽい」「楽しい」といった印象を与えられます。
また、距離が合っても一目で判読できる文字の大きさの目安を知っておくことも重要です。具体的には、下記の表を参考にしてください。
| 視距離 | 和文文字高 | 英文文字高 |
| 30mの場合 | 120mm以上 | 90mm以上 |
| 20mの場合 | 80mm以上 | 60mm以上 |
| 10mの場合 | 40mm以上 | 30mm以上 |
| 4~5mの場合 | 20mm以上 | 15mm以上 |
| 1~2mの場合 | 9mm以上 | 7mm以上 |
▲国土交通省「公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドライン」p58より抜粋