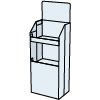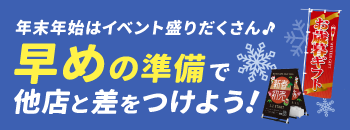のぼりを手作りしてみよう

自作する前に知っておきたいのぼり旗の基礎知識
文化祭などでのぼり旗を手作りする必要がある場合は、お店に使われる既製品のぼりのデザインなども参考にすると、デザインのアイデアも出しすいためおすすめです。また、のぼり旗を手作りするとなるとポンジなどの布生地、アクリル絵の具、布製テープなどを準備する必要があります。
自分で手作りする他には、印刷業者に発注する方法もあります。のぼりキングでのぼり旗を発注する場合、おおよそ下記の価格がかかります。また、のぼり旗を手作りする場合の費用の目安も以下の通りです。
| のぼり旗の種類 | 価格・費用(税込) |
| レギュラーのぼり旗 | 1,296円 |
| 手作りレギュラーのぼり旗 | 2,700円 |
| ミニのぼり旗 | 990円 |
| 手作りミニのぼり旗 | 1,600円 |
レギュラーのぼり旗とミニのぼり旗はどちらも手作りするよりも発注した方が価格を安く抑えやすく、作業する手間も省けるのでコスパがいいです。しかし、ミニのぼり旗は使用する生地を画用紙などに代用しやすいため、素材の選び方次第では手作りした方が発注するよりもお得になります。手間やクオリティを考えて、手作りにするか発注にするかを考えてみるとよいでしょう。
印刷所における実際の製作工程
工場ではどのようにのぼり旗が製作されているのか、のぼり旗を手作りする際にどのようなことに気を付けたら良いのか、気になっている方もいるかもしれません。ここでは、のぼり旗の製作工程をご紹介します。
1. 生地を液体に浸す
特殊な液体に生地を浸します。この処理をすることで、印刷する際ににじまずインクを乗せることができます。
2. デザインを印刷する
生地に直接印刷できるプリンターを使い、デザインを印刷します。
3. 生地を裁断する
印刷が終わった生地を裁断します。熱を帯びたカッターを使うことで、裁断した瞬間に生地の断面が固まってほつれを防ぎます。
4. チチを付ける
のぼり旗の生地部分とポールをつなげる役割を果たす輪っか状のチチ。チチを生地に取り付けたら完成です。
のぼり旗を手作りしてみよう
布とアクリル絵の具で作る
【準備するもの】
- 作りたいサイズの布やシーツ(屋外…オックス/屋内…シーチング)【手芸店】
- チャコペン【手芸店】
- 布製(粘着)テープ【ホームセンター】
- アクリル絵の具【文房具屋】
- 筆【文房具屋】
- 好きなフォントで印刷した文字の見本
1. 作りたい大きさに布を断つ

まずは布やシーツを作りたいのぼり旗の大きさに合わせて裁断します。旗のサイズは縦横比1:3になるように作られていることが多いです。一般的なサイズである180cm×60cmで作る場合、布を二つ折りにして作るため180cm×120cmの大きさが必要になります。
2. 文字の下書きをする

書きたい文字をバランスよく下書きしていきます。好きなフォントで1文字1枚ずつ印刷して準備しておくと下書きがしやすくなります。裁断した布に文字を印刷した紙を並べたら、紙と布の間にカーボン紙を挟み、紙の上からチャコペンで布に写していきます。イラストを入れようと考えている方は、ここでイラストも転写するのがおすすめです。
3. アクリル絵の具で色を塗る

生地の色との相性を考えて、好きな色のアクリル絵の具で色を塗っていきます。アクリル絵の具は水の量を調節することが大切です。水が少なすぎると絵の具が乾いてから崩れてしまう可能性があるため適度に調整しましょう。水の量と絵の具は1:2くらいの量で混ぜることを目安にして調整していくときれいに塗りやすいです。一度塗ったら乾かし、2~3回重ねて塗るときれいな発色になりますよ。裏面にも同様に塗っていきます。
4. チチを取り付ける

布を二つ折りにして形を整え、チチを取り付けます。チチには、布製テープをカットして輪っか状にしたものを使います。のぼり旗の上の辺に3~4か所、縦の辺に5~6か所バランスよく取り付けていきます。チチの輪っか部分があまりに太すぎるとのぼり旗がだらんとなり、きつすぎるとポールを通すのが難しくなってしまうので、取り付けるポールや竿の太さに合わせてチチの太さを決めましょう。
5. 手作りのぼり旗の仕上げ

縫い代1cmを内側に折り曲げ、アイロンでしっかり型をつけます。チチを仮留めして、三辺をミシンで縫うか、ボンドなどで接着します。最後にポールに通したら完成です。
店内用のポップも手作りできる
店内の商品横に置いてあるのぼり旗と同じ形のポップも、100円均一などで買える画用紙やシール用紙を使って、手軽に作ることができます。室内など雨に濡れる心配もなく、できるだけコストを抑えたい方は、POP用紙を使うことができます。POP用紙はマジックペンなどで自由に描くことができるためおすすめです。
今回はハチマキ、シール用紙、ストローを使ったポップの作り方をご紹介します。
【準備するもの】
ハチマキ(100円均一)
シール用紙(100円均一)
ストロー(100円均一)
1. ハチマキを裁断

作りたいポップのサイズに合わせてハチマキを裁断します。ハチマキではなく白い布でも大丈夫ですが、既製品のハチマキだとほつれないように処理してあるのでより手軽に作ることができます。
2. シール用紙に文字を印刷する

商品名や宣伝したい内容をシール用紙に印刷します。文字だけではなく写真やイラストも印刷してみてもいいですね。
3. シールをハチマキの両面に貼る

文字やイラストを印刷したシールをハチマキの両面に貼り付けます。このときシールを切ったときの余白部分をとっておくと、チチとして使うことができます。
4. ストローで支柱を作る

好きな長さにストローをカットし、上の辺と縦の辺に使うストローを連結させます。ストローの中に割りばしや竹串を入れると支柱としての強度が上がります。割りばしの上部に切り込みを入れてワイヤーを巻き、上の辺に使うストローに結び付けると連結できます。
5. 店内用POPの仕上げ


シール用紙の余った部分を使ってチチを取り付けます。上の辺に3か所、縦の辺に5か所程度バランスよく取り付けましょう。紙粘土やクリップを使うと土台になります。
メッセージが伝わりやすいのぼり旗を自作するコツ
屋外に設置するのぼり旗の場合、飲食店の近くを車で通るときに一瞬でパッと目に入るようなデザインを考える必要があります。似た商品や業種ののぼり旗を検索してみると、手作りする際の参考になるのでおすすめです。ただし、そのまま完全に真似をして作らないように注意しましょう。のぼりのデザインを作る時のポイントもついてはこちらをご覧ください。
① 大きい文字で太めのフォント
遠くから見たときにわかりやすいように文字は大きく、太いフォントを下書きしましょう。小さい文字だと読み取りにくいので、最小限の情報を大きい文字で書くようにしましょう。また、フォントは明朝体のように細いものよりも、ゴシック体のように太いもので書いた方が読み取りやすいです。
また、商業施設でのぼり旗を使う場合は、雰囲気に合ったフォントを選ぶことも大切です。子供向けのお店や教室であれば角ばったフォントよりも丸みを帯びたもの、和食のお店であれば筆で書いたようなフォントなど。読みやすさと雰囲気の二つを考えてフォントを選ぶと、目立つのぼり旗にぐっと近づきます。
② 文字数を多くしすぎない
のぼり旗に入れる文字数は多くしすぎてしまうと伝えたい情報がわかりづらくなってしまうため、伝えたいことだけを掲載できるように文字数を調整しましょう。
③ 色の数を使いすぎない
カラフルなのぼり旗は目につきやすいイメージがあるかもしれませんが、色の数を多く使いすぎてしまうとまとまりがないのぼり旗になってしまいます。使う色は多くても3色くらいにし、違う系統の色を使うよりも同系色でまとめたほうが良いでしょう。
④ 写真を使うときは大きいものを
のぼり旗に写真を使いたいときは、小さい写真をいくつも使うのではなく、一番見てもらいたい写真を大きく一つだけ掲載するようにしましょう。文字数や色の数と同じように、情報を欲張るのではなくシンプルにまとめることで目立つのぼり旗を作ることができます。
まとめ
のぼりキングでは、のぼり旗のデザインデータをお客様に作成いただく「データ入稿」プランや「WEB上デザイン」プランの場合、定番サイズのレギュラーのぼり旗を1枚1,296円(税込)から作れます。1種類あたりの数量が増えるほどさらに単価も安くなります。デザインはオリジナルにしたいけど、のぼり旗本体までは手作りするには時間や労力をかけられない方におすすめです。
また、のぼり旗の種類によっては既製品の価格と手作りの費用を比べて、お得な手段を選びましょう。
のぼり旗の用途が決まっていて、手作りだと費用や手間がかかる場合は、既製品を探してみることもおすすめです。のぼりキングなら12,000点以上のデザインの中から既製品のぼり旗を選べるため、手作りせずとも用途に合ったのぼり旗を見つけることができます。

※弊社にデータの制作から依頼される場合は、単価とは別にデータ制作費用が発生いたします。